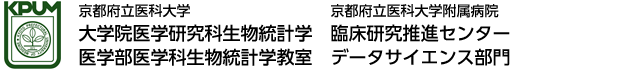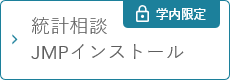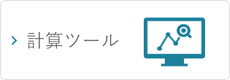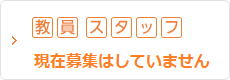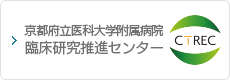京都府立医科大学 生物統計学教室は臨床・疫学研究の計画・実施、データ信頼性確保を行っています。
教 育(2024年度)
鴨川統計集会 (Kamogawa Statistical Conference; KSC)
当教室では大学院統合医科学専攻の演習として、「鴨川統計集会」(Kamogawa Statistical Conference; KSC)を実施しております。
- 4/9 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 生物統計学教室
中田 美津子「条件付き推論の妥当性について」
1972年にD.R.Coxにより発表された比例ハザードモデル論文は生物統計の最も影響力ある論文の1つであるが、モデル構築の礎となったのはFisherの正確検定であった。FisherとCoxの類似点ならびに条件付き推論の妥当性について考察する。内藤 あかり「層間のベースラインリスクの違いを考慮した情報共有を行うバスケット試験デザイン」
ベースラインリスクが異なる被験者を組み入れる臨床試験では、ベースラインリスクによる層ごとの解析は検出力が十分でない場合がある。一方で、ベースラインからの変化量の解析、またはモデルベースの解析は、検出力は高くなるが層間で治療効果が等しいことを仮定する。本発表では、中間的なアプローチとしてベースラインリスクの違いを考慮した上で治療効果の類似度に応じて層間で情報共有を行う2値評価項目の単群バスケット試験デザインを提案する。- 5/14 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 生物統計学教室
堀口 剛「時間イベント型評価項目・単群臨床試験に対するベイズ流検出力に基づく標本サイズ設計」
全生存期間(OS)や無増悪生存期間(PFS)などのイベントまでの時間(time-to-event)をアウトカムとした単群臨床試験におけるベイズ流標本サイズ設計を考える。具体的には、ヒストリカル対照と試験治療の生存関数に比例ハザード性が成り立つことを仮定した上で、ハザード比に関する事後確率及び事前予測確率を用いたベイズ流検出力に基づく標本サイズ設計を提案する。発表では、方法の詳細とともに複数のシナリオ設定のもとで評価した動作特性の結果を示す。小城 一翔「日本人における潰瘍性大腸炎治療時の5-ASA製剤不耐の予測モデル構築」
潰瘍性大腸炎治療における第1選択薬は5-ASA製剤であり、再燃を予防するためにも長期にわたり服用する必要がある。しかし、下痢や血便、発熱などの副作用により5-ASAの継続投与が困難になる、不耐と呼ばれる症状を起こす患者が1割程度存在し、その数は経年的に増加傾向である。不耐が起きるリスクが高い患者を予測することができれば、より安全な治療を目指すことができる。本発表では、5-ASA不耐の発生を予測するための予測モデル構築過程について紹介する。- 7/9 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 生物統計学教室
手良向 聡「ベイズ流決定理論に基づく臨床試験は実践できるのか」
Spiegelhalter DJ, et al. (2004) は、Schools of Bayesiansとして以下の4つの接近法を提示している:1.経験(empirical)ベイズ、2.参照(reference)ベイズ、3.適正(proper)ベイズ、4.決定理論的(decision-theoretic)ベイズ。決定理論は、効用関数を定義したうえで、期待効用の最大化が最適な意思決定であるという規範モデルに基づく。効用関数をどう決めるかが最大の課題であるが、過去の事例では多種多様である。本発表では、ベイズ流決定理論に基づく臨床試験を実践的な立場から論じる。- 9/10 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 第6会議室
山本 景一「健康・医療・介護分野のマルチモーダルデータの統合利用: PHRデータ流通基盤構築プロジェクト ”PHOENICS”の経験から」
デジタルヘルス技術の進展により、診療データに加え、身体活動・睡眠・心拍・服薬遵守他の多様な日常の健康関連マーカーを頻回かつ経時的に測定することが可能となっている。これらは数値/画像/テキスト/音声など複数種類のデータ(モダリティ)を組み合わせて実装される。医療のマルチモーダルデータを統合利用するためには、検索拡張生成(RAG)他の新しい技術を活用するととも情報標準化が課題となる。AMED「医療高度化に資する分散管理型PHRデータ流通基盤に関する研究開発」のPHRデータ流通基盤構築プロジェクト(PHOENICS)の経験から、マルチモーダルデータ統合利用のための現状と課題について概説したい。- 10/8 (火) 16:30-18:00 臨床医学学舎6階 生物統計学教室
横田 勲「ネスティッドケースコントロール 研究における 重いタイがみられる場合の解析法」
ネステッドケースコントロールデザインでは、イベントが発生するたびに対照群がリスクセットサンプリングされることが多いが、実際にはイベント発生が一定間隔で測定される場合、同時点でイベントが複数例含まれるタイデータが生じることがある。本研究では、マッチング比やタイの重さが推定に与える影響を調べるため、条件付ロジスティックモデル、無条件ロジスティックモデル、重み付き部分尤度法のバイアスや統計的効率性をシミュレーションにより比較した。- 11/12 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 第6会議室
西村 友樹
亀山 堅司
- 12/10 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 第6会議室
上杉 まどか
垣淵 大地
喜多 優介
- 1/14 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 生物統計学教室
川脇 拓磨
鶴川 慎一郎
- 2/18 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 第6会議室
塩住 忠春
標 玲央名
- 3/11 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 生物統計学教室
山出 健博
中田 康貴
当教室では学内で以下の講義を担当しております。
大学院統合医科学専攻(総合コース専門領域)
【講義A】・・・1年次
- 1) 研究実施計画書、評価項目、統計的仮説、ランダム化
- 2) 標本サイズ設定、解析対象集団、中間解析、サブグループ解析
- 3) 観察研究のデザイン
【講義B】・・・2年次
- 1) 推測統計学の基礎、基本となる統計手法
- 2) 予後因子解析、予後指標の構築、代替評価項目の評価
- 3) メタアナリシス、医療経済評価
【演習】・・・1~2年次
鴨川統計集会を参照してください。
【特講】・・・1~3年次
生物統計学分野における最先端の研究について講義・演習を行う。
【論文指導】
医学研究の統計的方法論について課題を設定し、文献レビュー、既存手法の整理、新規手法の開発・提案などを行えるように指導する。また、医学研究データの統計解析に基づいて、予後因子の同定、予後指標の構築、予防・診断・治療効果の推定を正しい方法で行えるように指導する。
大学院統合医科学専攻
(総合コース共通領域・がんプロフェッショナル養成専門コース)
【医学研究方法概論】 「医学研究における統計学の役割(手良向)」
6/18 18:00~19:30 ハイブリッド(第2講義室、Zoom)
医学研究において頻度流統計学(主に統計的仮説検定、P値、信頼区間)を正しく利用するための心得について解説した上で、将来主流になるであろうベイズ流統計学の基本的考え方と可能性を解説する。
【統合医科学概論】 「予後因子解析と臨床予測モデル構築(手良向)」
10/9 18:00~19:30 ハイブリッド(第2講義室、Zoom)
予後/リスク因子解析は観察研究等のデータから重要な情報を得る基本的手法の1つである。また、患者をリスクグループに分類する臨床予測モデルは臨床に有用なツールとなり得る。本講義では、予後/リスク因子解析および臨床予測モデル構築の方法論を基礎から解説する。
大学院医科学専攻(修士課程)
【医科学研究法概論】「医療統計学」と合同実施
7/17 3限 (中田) 北臨床講義室、 11/20 3限(中田) 北臨床講義室
臨床研究およびメタアナリシスの方法論および統計学的推論の基本的考え方を理解する。
【医科学演習】
臨床試験論文を正しく読むために、CONSORT声明(臨床試験報告ガイダンス)に基づいて試験デザイン、統計解析手法、結果の解釈などについて指導する。
保健看護学研究科(博士課程)
【統計方法論特別講義】
10/6 10:00~17:00、 11/3 10:00~17:00
11/4 13:00~17:00、 11/10 13:00~17:00
研究計画の方法として、臨床研究(臨床試験・観察研究)の方法論を理解した上で、研究実施計画書の概要が作成できることを目標とする。統計解析の方法として、データの適切な要約と視覚化の仕方、統計手法を正しく理解した上で、研究デザインおよびデータに対応した統計解析が行えることを目標とする。
大学院特別講義
『経時測定データの統計解析』
12/18(水) 18:00-19:00 基礎医学学舎第2講義室(対面講義)
講師: 阿部 貴行 先生
京都女子大学 データサイエンス学部 教授
概要:
医学部医学科
【生物統計学】
生物統計学は、臨床・疫学研究の方法論の基礎となる学問である。臨床・疫学研究の計画・デザインの段階から統計解析・報告の段階まで、生物統計学の知識とその活用が必須となる。本講義では、数学的な厳密性を保ちつつ、実践における有用性を重視して、生物統計学に基づく科学(ヘルスデータサイエンス)の考え方を講義する。
第3学年
| 1. 10/8 | 3限 | 臨床研究と生物統計学(手良向) |
| 2. 10/8 | 4限 | データの記述と推測(中田) |
| 3. 10/15 | 3限 | 頻度流統計学とベイズ流統計学(堀口) |
| 4. 10/15 | 4限 | 2群の比較(中田) |
| 5. 10/22 | 3限 | 分散分析と一般線形モデル(中田) |
| 6. 10/22 | 4限 | 交絡バイアスとその調整(松山教授・非常勤講師) |
| 7. 11/5 | 3限 | 生存時間解析(堀口) |
| 8. 11/5 | 4限 | ロジスティック回帰分析とコックス回帰分析(手良向) |
【医療統計学】・・・第5学年
| 7. 7/3 | 3限 | 臨床試験デザイン(1)(堀口) | |
| 8. 7/3 | 4限 | 臨床試験デザイン(2)(堀口) | |
| 9. 7/17 | 3限 | 観察研究デザイン (中田) | |
| 20. 11/13 | 4限 | 評価尺度の信頼性と妥当性(中田) | |
| 21. 11/20 | 3限 | メタアナリシス・費用効果分析 (中田) | |
| 22. 11/20 | 4限 | 診断法の統計的評価(講義の確認テスト)(手良向) |
【総合講義:臨床薬理学】・・・第5学年 11/21 3限 「臨床試験のデザイン(手良向)」
臨床試験のデザイン、および確率、統計学、AIの関係について講義する。