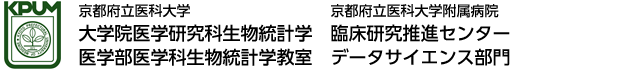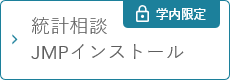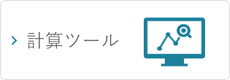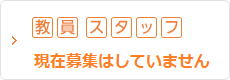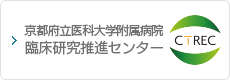京都府立医科大学 生物統計学教室は臨床・疫学研究の計画・実施、データ信頼性確保を行っています。
教 育(2025年度)
鴨川統計集会 (Kamogawa Statistical Conference; KSC)
当教室では大学院統合医科学専攻の演習として、「鴨川統計集会」(Kamogawa Statistical Conference; KSC)を実施しております。
- 4/8 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 第6会議室
中田 美津子「臨床試験シミュレーションソフトFACTSの紹介」
FACTSは、米国の統計コンサルタント会社Berry Consultantsが開発したシミュレーションソフトで、用量漸増試験、用量探索試験、アダプティブ試験、バスケット試験、アンブレラ試験、プラットフォーム試験など数多くの複雑で革新的な臨床試験のシミュレーションを行える。操作はプログラミング不要のGUIで、C++言語を用いているため処理が早い。今般、当教室で教育目的またはアカデミア内での使用に限定したFACTSライセンスを取得した。当日はデモを交えてFACTSの機能を紹介する。内藤 あかり「A basket trial design accounting for baseline risk across strata」
ベースラインリスクが異なる被験者を組み入れる臨床試験では、ベースラインリスクによる層ごとの解析は検出力が十分でない場合がある。一方で、ベースラインからの変化量の解析、またはモデルベースの解析は、検出力は高くなるが層間で治療効果が等しいことを仮定する必要がある。本発表では、中間的なアプローチとしてベースラインリスクの違いを考慮して治療効果の類似度に応じて層間で情報共有を行う、2値評価項目の単群バスケット試験デザインを提案し、シミュレーション結果を発表する。- 5/13 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 生物統計学教室
堀口 剛「欠測データへの対処と多重代入法の概要」
臨床疫学研究において、欠測データへの適切な対処は解析の信頼性という点で重要である。本発表では、データベース(JROAD)研究を背景に、欠測を無視する方法から補完や直接推定に至るいくつかの手法を概観する。特に、Rubinにより提案された多重代入法の考え方と実装手法(Joint modeling、EMB、FCS)に焦点を当て、それぞれの前提、長所、短所を比較する。また、外部情報を活用した近年のアプローチも紹介する。三島 遼「Coarsened Exact Matchingの紹介および分類木との組み合わせ」
Propensity Score Matchingは臨床研究において広く利用されている交絡調整法の1つである。しかし、マッチング条件を厳しくすることが必ずしも共変量バランスの改善に直結しない、PSM Paradoxが生じうると指摘されている。本研究では、その解決策として提案されたCoarsened Exact Matchingを紹介する。また、Coarsened Exact Matchingと分類木を組み合わせた新しいマッチング手法について検討した結果をシミュレーション実験に基づいて報告する。- 6/10 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 第6会議室
中田 美津子「項目反応理論(IRT)入門」
項目反応理論は、TOEICやTOEFLに使用されている現代テスト理論の要である。従来の古典テスト理論が受験者と項目に依存するため、未来の試験には適用できないのに対し、項目反応理論は受験者特性という潜在因子を仮定することにより、テストの等化を可能にした。これにより、受験者特性に応じた項目を項目プールより選択できるようになり、コンピューター適応型試験が行えるようになった。当日は、IRTの基本的なモデルと推定法を紹介する。兼松 友希「回帰または機械学習を用いた臨床予測モデルの報告に関するTRIPOD声明の更新」
臨床予測モデルに対する関心は高い一方で,報告される臨床予測モデルについての信頼性と安全性に懸念がある.TRIPOD2015声明は臨床予測モデルの報告基準を示したが,近年のAIや機械学習の普及により新たな課題が生じた.これに対応するため,回帰・機械学習モデルの両方に対応し,かつ,透明性と信頼性の高い報告を促すTRIPOD+AI声明が発表された.本発表ではTRIPOD2015声明からTRIPOD+AI声明への更新内容について紹介する。- 7/8 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 生物統計学教室
手良向 聡「統計学における客観性:ベイズ主義の立場から」
科学は客観的であるべきであるという基調の下、統計学における主観性と客観性について近年議論が盛んである。頻度主義からのベイズ主義に対する最大の批判は事前分布の主観性である。主観ベイズ主義に対して、客観ベイズ主義は、できるだけ明確かつ一般的な原則を用いた透明性のある方法で事前分布を正当化しようとする強い動機を持っている。本発表では、統計学における哲学的接近法、統計学に基づく臨床試験方法論における客観性について議論する。- 9/16 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 生物統計学教室
内藤 あかり「単群臨床試験における層ごとのベースラインリスクを考慮した情報借用」
重症度等のベースラインリスクが異なる被験者を組み入れる単群臨床試験では、ベースラインリスクによる層別解析は検出力が十分でない場合がある。そこで、検出力向上のためにバスケット試験における情報借用のように層間で情報借用を行うことを考える。本発表では、(Fujikawa et al. Biom J. 2020;62:330-8) の ベイズ流バスケット試験デザインの拡張によりベースラインリスクの違いを考慮して層間で情報借用を行うことが可能な方法について、他手法と比較したシミュレーション結果を報告する。三島 遼「ベイズ流臨床試験デザインにおける第一種の過誤確率および検出力の評価」
ベイズ流臨床試験デザインでは、事前情報の活用や中間解析の実施により、第一種の過誤確率が増大する懸念がある。複雑なデザインでは適切な症例数を解析的に導出することが難しいため、シミュレーションにより評価することが一般的である。本発表では、第一種の過誤確率および検出力を評価することを目的として、演者が開発したSASプログラムを紹介する。また、それを用いたシミュレーション実験の結果を報告する。- 10/14 (火) 16:30-18:00 臨床医学学舎6階 第6会議室
横田 勲「正確な単群がん第Ⅱ相逐次試験デザイン」
小児がんなどの比較的小標本で行う単群第II相試験では、有効性評価を逐次的に行えるほうが早期の意思決定につながる。本研究では、参加者数によらず一定の閾値で有効と判断する逐次デザインを提案する。大標本近似に頼らずαエラー率を正確に制御でき、さらに到達不可能な場合に中止を判断する決定的打ち切り法を組み合わせることで、効率的かつ解釈しやすい設計を実現した。- 11/11 (火) 16:00-16:30 臨床医学学舎6階 生物統計学教室
垣淵 大地「胸腺上皮性腫瘍における癌関連線維芽細胞(CAF)の発現と臨床病理学的因子の関」
近年、癌関連線維芽細胞(CAF)は悪性腫瘍の新規治療標的として注目されている。本研究では当院で外科切除された胸腺上皮性腫瘍120例を対象に、CAFマーカーであるα-SMAとVimentinの免疫染色像をデジタル画像解析で定量化し、病理学的因子および予後との関連を検討した。両マーカーの発現は高悪性度・進行病期で高値を示し、高発現群では全生存期間(OS)および無再発生存期間(RFS)が有意に短かった。胸腺上皮性腫瘍においてもCAFは有望な治療標的となり得ることが示唆された。- 12/9 (火) 16:00-16:30 臨床医学学舎6階 第6会議室
岩井 宏樹「80歳以上の大腸癌に対する大腸切除術におけるロボット支援手術と腹腔鏡手術の比較検討」
ロボット支援手術は精緻な操作性と安定した視野を有し、高齢者大腸癌に対する安全で低侵襲な手術手技としての有用性が期待されている。高齢化が進む地域の市中病院において施行された80歳以上大腸癌待機的大腸切除術140例を対象に、ロボット支援手術68例と腹腔鏡手術72例の成績を比較した。ロボット群では出血量減少、在院日数短縮、開腹移行率低下を認め、合併症率や再発率に有意差はなかった。ロボット支援手術は80歳以上の高齢者において良好な短期成績を示し、安全かつ有用な術式であることが示唆された。- 1/13 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 生物統計学教室
標 玲央名
土橋 亮太
鶴川 慎一郎
- 2/10 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 第6会議室
川脇 拓磨
長谷川 洋平
谷口 雄基
- 3/10 (火) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 生物統計学教室
喜多 優介
森川 咲
西村 優佑
生物統計学セミナー
12/15 (月) 16:30-17:30 臨床医学学舎6階 生物統計学教室
講師: 大庭 幸治 先生
東京大学大学院 情報学環 教授
『仮想ストラテジーを用いたestimandに対するcontrolled multiple imputation の利用』
ICH E9(R1)の通知以降、研究者主導臨床試験においても estimand を議論する機会が増え ている。中でも、中間事象、中間事象に対処するためのストラテジーに関しては、関係する 研究者とのコミュニケーションが重要となる。とりわけ仮想ストラテジーを採用する場合 には、中間事象後の未観測データに対し臨床的に意味のある仮想的状況を設定することが 求められると同時に、設定した仮定が試験結果の結論に与える影響に関する頑健性を、感度 分析を通じて厳密に評価する必要がある。このような感度分析を含めた議論を丁寧に行う ためには、統計的にも臨床的にも解釈のしやすい方法が必要であると考える。 1 つの有用なツールだと考えられるのがcontrolled multiple imputation(cMI)を用いた方法 である。cMI は、National Research Council による欠測ガイダンスが出版された当初、 Mallinckrodt ら 1)や Carpenter ら 2)によって提案され、主に欠測データに対する NMAR (Not Missing At Random) を仮定した解析として利用されてきた。Pattern Mixture Modelの枠組み で、臨床的解釈が可能な欠測アウトカムの推移パターンを体系的に導入することにより、 様々な仮想的推移に基づいた評価を可能とする。近年では、Croら3)によってICH E9(R1)の 要請に適合する感度分析のフレームワークとして具体的に整理されている。 本抄読会では、個人的に経験した臨床試験の事例を踏まえながら、cMIを用いた仮想スト ラテジーに基づく estimand の評価および感度分析について解説し、関連する議論について 紹介したい。
6/25 (水) 16:00-17:30 臨床医学学舎6階 生物統計学教室
講師: 服部 聡 先生
大阪大学大学院医学系研究科 医学統計学 教授
『区分加速モデルによる癌免疫療法臨床試験の統計解析』
癌免疫療法はその作用機序から効果発現までに一定の期間(lag time)を要し、臨床試験において、lag timeまでは対照群と生存曲線が一致し、その後治療効果が見られることがよく観察される。Lag timeまでの生存曲線の一致は比例ハザード性の不成立を意味し、さらに、一定の割合の症例が免疫療法の効果を得る機会を持たないことを意味する。本研究では、平均的な治療効果の要約に加えて、上述のような症例の特徴づけを統一的に行う統計的方法の試みについて議論する。
当教室では学内で以下の講義を担当しております。
大学院統合医科学専攻(総合コース専門領域)
【講義A】・・・1年次
- 1) 研究実施計画書、評価項目、統計的仮説、ランダム化
- 2) 標本サイズ設定、解析対象集団、中間解析、サブグループ解析
- 3) 観察研究のデザイン
【講義B】・・・2年次
- 1) 推測統計学の基礎、基本となる統計手法
- 2) 予後因子解析、予後指標の構築、代替評価項目の評価
- 3) メタアナリシス、医療経済評価
【演習】・・・1~2年次
鴨川統計集会を参照してください。
【特講】・・・1~3年次
生物統計学分野における最先端の研究について講義・演習を行う。
【論文指導】
医学研究の統計的方法論について課題を設定し、文献レビュー、既存手法の整理、新規手法の開発・提案などを行えるように指導する。また、医学研究データの統計解析に基づいて、予後因子の同定、予後指標の構築、予防・診断・治療効果の推定を正しい方法で行えるように指導する。
大学院統合医科学専攻
(総合コース共通領域・がんプロフェッショナル養成専門コース)
【医学研究方法概論】 「医学研究における統計学の役割(手良向)」
6/17 16:10~17:40 オンライン講義(Zoom)
医学研究において頻度流統計学(主に統計的仮説検定、P値、信頼区間)を正しく利用するための心得について解説した上で、将来主流になるであろうベイズ流統計学の基本的考え方と可能性を解説する。
【統合医科学概論】 「予後因子解析と臨床予測モデル構築(手良向)」
10/6 18:00~19:30 オンライン講義(Zoom)
予後/リスク因子解析は観察研究等のデータから重要な情報を得る基本的手法の1つである。また、患者をリスクグループに分類する臨床予測モデルは臨床に有用なツールとなり得る。本講義では、予後/リスク因子解析および臨床予測モデル構築の方法論を基礎から解説する。
大学院医科学専攻(修士課程)
【医科学研究法概論】「医療統計学」と合同実施
10/8 4限 (中田) 北臨床講義室、 10/22 3限(中田) 北臨床講義室
臨床研究およびメタアナリシスの方法論および統計学的推論の基本的考え方を理解する。
【医科学演習】
9/25、 11/28
臨床試験論文を正しく読むために、CONSORT声明(臨床試験報告ガイダンス)に基づいて試験デザイン、統計解析手法、結果の解釈などについて指導する。
保健看護学研究科(博士課程)
【統計方法論特別講義】
10/4 10:00~17:00、 11/8 10:00~17:00
11/24 13:00~17:00、 12/20 13:00~17:00
研究計画の方法として、臨床研究(臨床試験・観察研究)の方法論を理解した上で、研究実施計画書の概要が作成できることを目標とする。統計解析の方法として、データの適切な要約と視覚化の仕方、統計手法を正しく理解した上で、研究デザインおよびデータに対応した統計解析が行えることを目標とする。
大学院特別講義
『観察研究における傾向スコア法の利用と注意点』
12/15(月) 18:00-19:00 基礎医学学舎 第2講義室(対面講義)
講師: 大庭 幸治 先生
東京大学大学院 情報学環 教授
概要:観察研究で結果を正しく解釈するためには、ランダム化の欠如によって生じる交絡バイアスの調整が不可欠です。 本特別講義では、その強力な統計的ツールである傾向スコア(Propensity Score)の基本的な概念と算出方法を分かりやすく解説します。 さらに、バイアスを抑制し因果効果を推定するためのマッチング、重み付けといった実践的な利用法、そして利用上の重要な注意点もしっかりとお伝えします。 「傾向スコアって何?」という方から、日頃から利用していて具体的な課題を抱える方まで、幅広い参加者を対象とした実践的な知識を提供します。
医学部医学科
【生物統計学】
生物統計学は、臨床・疫学研究の方法論の基礎となる学問である。臨床・疫学研究の計画・デザインの段階から統計解析・報告の段階まで、生物統計学の知識とその活用が必須となる。本講義では、数学的な厳密性を保ちつつ、実践における有用性を重視して、生物統計学に基づく科学(ヘルスデータサイエンス)の考え方を講義する。
第3学年
| 1. 10/7 | 3限 | 臨床研究と生物統計学(手良向) |
| 2. 10/7 | 4限 | データの記述と推測(中田) |
| 3. 10/14 | 3限 | 頻度流統計学とベイズ流統計学(堀口) |
| 4. 10/14 | 4限 | 2群の比較(内藤) |
| 5. 10/21 | 3限 | 分散分析と一般線形モデル(中田) |
| 6. 10/21 | 4限 | 交絡バイアスとその調整(松山教授・非常勤講師) |
| 7. 11/4 | 3限 | 生存時間解析(内藤) |
| 8. 11/4 | 4限 | ロジスティック回帰分析とコックス回帰分析(手良向) |
【医療統計学】・・・第5学年
| 9. 7/23 | 4限 | 評価尺度の信頼性と妥当性 (中田) | |
| 10. 7/30 | 3限 | 臨床試験デザイン(1)(堀口) | |
| 11. 7/30 | 4限 | 臨床試験デザイン(2)(堀口) | |
| 19. 10/8 | 4限 | 観察研究デザイン(中田) | |
| 20. 10/22 | 3限 | メタアナリシス・費用効果分析 (中田) | |
| 21. 10/22 | 4限 | 診断法の統計的評価(講義の確認テスト)(手良向) |